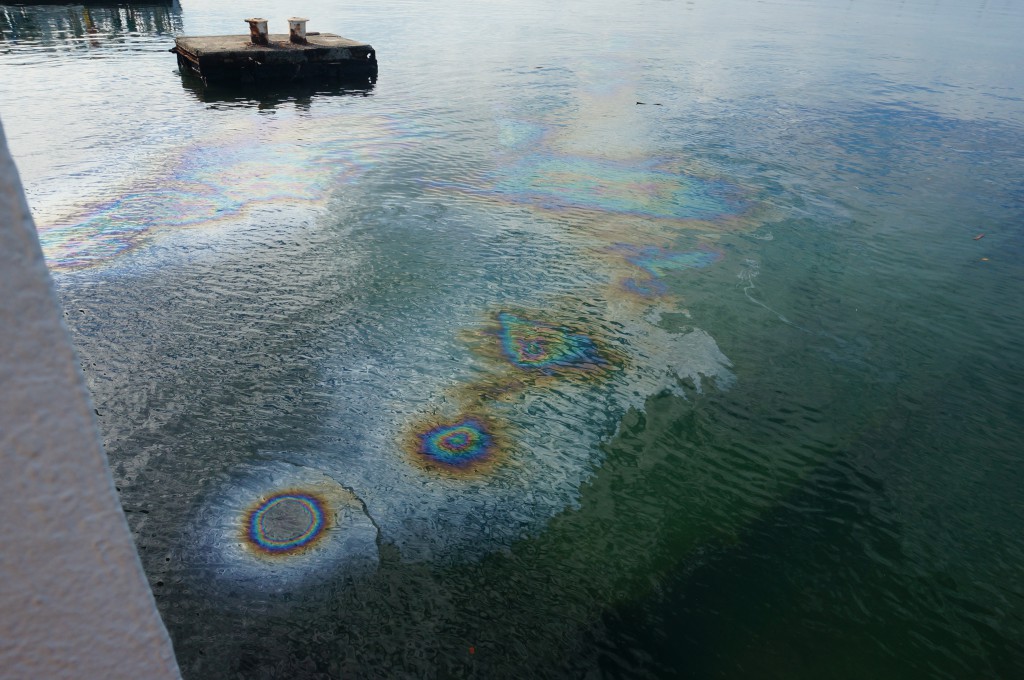この事件に関心がある方々で、チーム側(前回定義した通り、当時の学生チームのリーダー達)に同情的な意見を持つ方は、こんなふうに考えるのではないだろうか。
「鳥人間コンテストは最終的には湖に落下する競技であり、どれほど注意深く人力飛行機を作っても、パイロットが負傷する可能性はある。その結果、負傷の程度が予想以上だったとしても、パイロットはそれをもともと承知していたはずではないか」
もし私が彼らの側だったとしても、そのように主張するだろう。しかし、彼らの主張はそれとは大きくかけ離れていた。今回は、彼ら「チーム側」の主張を見てみよう。
「責任は読売テレビにあって参加者にはない」と主張
責任に関する、チーム側の主張はこうだ。KITCUTSは航空工学をかじっただけの素人集団である。鳥人間コンテストは素人が出場する大会であり、そのためにプラットホームを設けて離陸を容易にし、誰でも気軽に参加できるようにしている。また、うまく飛べずに落ちるチームも毎回放送し、プラットホームから落下する様を見せて楽しませるという面もある。読売テレビが「素人である参加者に代わって機体の安全性を十分に審査・確認する義務を負っているものであり、参加者が高度な注意義務を負うことはない」と主張した(以下、斜体文字は答弁書原文引用)。
つまるところ、原告である川畑さんが「責任の一端はチーム側にもある」と主張したのに対し、チーム側は「自分達は素人であり、鳥人間コンテストは落ちることも楽しんでいるのだから、責任は自分達にはなく、読売テレビにある」と主張したわけだ。
第三者がこういうことを言ったら、おそらく多くの鳥人間コンテスト出場者は侮辱だと感じるだろう。鳥人間チーム、特に設計やチーム運営に当たる者は、未熟な大学生ながら必死に航空工学を学び、先輩や他のチームに教えを乞い、全力で人力飛行機を作り上げる。それが時には、はかなくも落下するからこそ、本物の悔し涙を流すのだ。
素人が誰でも気軽に参加して落ちることを楽しむ大会なんだから失敗してもいいだろう、事故があったら読売テレビのせいだ、などと考える者はいない。いくら裁判での反論と言っても、そこまで自分達の過去の活動を貶める必要があるのだろうか。
設計は適切だったか
原告側は、機体の設計ミスが破損の原因であると主張した。まずこの設計について見てみよう。
人力飛行機の主翼は、「主桁」と呼ばれる頑丈な構造に、発泡スチロールやフィルムで肉付けして作られるのが一般的だ。翼が折れないように大きな力に耐える主桁には、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)のパイプが使われる。航空宇宙分野やスポーツ用品で使われる材料で、「カーボン製」と言い換えた方が馴染みがあるかもしれない。
近年の人力飛行機は、翼の幅が30m前後と非常に大きい。大きくなるほど翼を曲げる力は強くなるので、頑丈なパイプを使わなければならない。しかし事故機の設計図を見ると、主翼が折れた箇所のパイプの直径は60mm未満しかない。一方、やはり30m前後の主翼幅がある多くのチームの図面を見ると、この付近のパイプ直径は100mm前後である。直径が6割程度しかないのだ。
丸パイプの場合、厚みが同じであれば強度は直径の2乗に比例する。直径が6割であれば、曲げに対する強度は1/3程度しかない。
念のため、複数の優勝経験チームの設計担当者に、この図面を見てもらった。彼らは絶句し、次に「この設計で、もつとは思えない」と口を揃えた。次いで、念のため設計プログラムを使って検証してもらったが、エラーが出てしまった。歪みを計算するためのプログラムなので、壊れるほど大きな歪みではプログラムの想定範囲を超えてしまったようだった。
「原告は人力飛行機を理解していない」と主張
チーム側の反論はこうだ。人力飛行機は、軽く作らなければ飛ぶことができない。パイプは細いほうが軽いのが当然だ。細ければ弱い、などということはない。細くてもパイプの厚みがあれば同じ強度は保てるのだ、と。
この反論も、鳥人間経験者や構造エンジニアであれば失笑ものだろう。「細いほうが軽い」「厚ければ強い」というのは正しい。しかし同時に「細いほうが弱い」「厚ければ重い」である。では「細くて厚い」パイプは重いのか、軽いのか。
先ほど説明した通り、厚みが同じならパイプの強度は直径の2乗に比例し、重量は直径に比例する。従って、厚みが同じで太さが6割のパイプは、強度が約1/3で、重量は6割となる。
次に厚みについて考えてみると、強度は厚みに比例し、重量も厚みに比例する。先ほどの「直径6割パイプ」の強度が元のパイプと同じになるようにするには厚みを3倍にすればよく、重量は約2倍になってしまうのだ。強度が同じなら、細くするとパイプは重くなるのである。軽く作るために細くしたのであれば、同じ材料で同じ強度を保つことは不可能なのだ。
さらに、チーム側はこう主張した。
「鳥人間コンテストディスタンス部門の主目的は、当然に飛距離を伸ばすことに求められる。原告のこれまでの主張は、鳥人間を飛行させ、飛距離を伸ばすという本来的な目的を忘れた、ただ機体の強度のみに注視した主張であり、前述のような人力飛行機の性質につき何も理解していないと言わざるを得ない。原告主張のように、ただ壊れないことのみに注目した機体(=抗力の観点しか考慮していない機体)を製作するのは至極簡単であり、非常に頑丈な材質を用いて機体を構築すれば足りるが、そのような重い機体が浮くはずもない。」
※原告側は「抗力」という観点での主張はしていないので、なぜ抗力が出てきたのかは不明。
「人力飛行機の素人集団」を自称する彼らがここまで言い切るのは驚きだが、およそ他の鳥人間チームの賛同を得られる内容ではない。誰も、絶対に壊れない機体を作れとは言っていない。鳥人間チームはいずれも、飛行前には壊れない程度の強度は備えるように設計している。なぜなら、飛行前に壊れてしまったら、飛距離を伸ばすどころか全く飛べないのだから。しかし人力飛行機は「浮くはずもない」どころか、滑走路から自力で離陸し、琵琶湖を往復することすらあるのだが、彼らは何を言っているのだろうか。
「試験飛行をしなくても安全確認は可能」と主張
原告側からは、チームが充分な試験飛行による確認を怠ったことも主張された。
一般的に、人力飛行機は鳥人間コンテストの前に試験飛行を行う。グライダーの滑走路などを借りて、まず地上を走行するところから開始。徐々に速度を上げ、プロペラや車輪、操縦装置などが正常に作動するか、主翼が設計どおりきれいにたわんでいるかなどを確認する。次いで、飛行速度まで速度を上げると、人力飛行機は滑走路から離陸する。このとき重心位置が悪いと急上昇して失速したり、いくら加速しても浮かなかったりするので調整する。最初は少し浮いたら下ろし、徐々に距離を伸ばして機体を調整しつつ、パイロットの訓練も行う。早朝の無風状態でなければできないため1日の走行・飛行回数は限られ、また天候にも左右されるため数か月かけて述べ数日間行われるのが一般的だ。
KITCUTSは、この試験飛行をほとんど行っていない。1回目は悪天候で延期。2回目は試験走行中に主翼が破損したため離陸に至らなかった。つまり、一度も「飛行中の荷重に主翼が耐えられること」を確認しないまま、本番に臨んだのである。前回説明した通り、この機体は鳥人間コンテスト本番で、車輪で滑走している最中に主翼が折れるほど弱かった。であれば、試験飛行で離陸を試みれば、その時点で主翼が折れていた可能性が高い。それをせずに「3回目の試験飛行をしなくても問題ない」と判断したことが重大だと、原告は主張しているわけだ。
なお、この点については読売テレビも関係している。読売テレビはKITCUTSの書類選考合格の付帯条件に「充分に試験飛行を行うこと」と明記している。この付帯条件は全チームに書かれているわけではなく、チーム個別に書かれたものだ。KITCUTSは読売テレビへの参加申請書に自ら「試験飛行を4回実施する」と明記しており、読売テレビはわざわざ合格通知で念を押している。もしかすると書類選考段階で主翼の強度に不安を持っていたのかもしれない。そして大会前日の機体検査(全チームに対して目視検査とヒアリングが行われている)で読売テレビはKITCUTSに試験飛行の結果を尋ね、「ふわっと浮いた」と聞いた、というのが読売テレビの主張である。
これに対するチーム側の主張は「試験飛行では浮いていない。浮いていないのだから『ふわっと浮いた』などと言うはずがなく、読売テレビは嘘をついている」というものだった。約束を守らなかったことを咎められたときの開き直りとして、これほど大胆なものを私は知らない。
そして、試験飛行を行わずに済ませた理由を挙げている。試験飛行をしているのは強豪チームが記録を伸ばすためであって、安全のためではない。安全性は設計で確認可能であり「原告が、飛行試験の意義・目的をはき違えていることは明らかである」と主張した。
何をかいわんや、である。現に機体は離陸前に自壊しており、設計だけでは安全性が確認できていないことは明らかだ。しかも試験走行の段階で主翼は壊れており、それで試験飛行を打ち切ったのだから、浮上しても壊れないことは確認できていない。皆さんは「ロープに試しにぶら下がったら体重で切れてしまった」のに、新しいロープを確認しないで登山に行くだろうか?問題は原告であるパイロットも含め、チームでどのような判断を行った結果、再試験なしで本番に臨むという意思決定がなされたかであろう。
さらに、チーム側はこうも主張する。「原告の主張は、費用も掛かり、物理的な場所を確保できなければ実施できない飛行試験を数回行うことが可能なチームでなければ鳥人間コンテストに参加してはならないと主張しているに等しい」と。しかし、鳥人間チーム経験者なら誰でもこう答えるだろう。「鳥人間に金と手間がかかるのは当たり前じゃないか」
ちなみに、東京都内の鳥人間チームはいずれも、静岡県や埼玉県の飛行場まで多額の費用をかけて通っている。大学と同じ北九州市内にある旧北九州空港の滑走路を無償で使用できるKITCUTSは、私から見れば羨ましい環境だ。
不自然すぎる主張
ずいぶん長くなってしまったが、これがチーム側の主張だ。私が要約し、意見を書き加えているからバイアスがかかっていることは否定しないが、出鱈目を書いたつもりはない。基本的に彼らの主張は上記の通りだ。読んで下さった方々はどう感じただろうか。
私は「いくら何でも、こんな支離滅裂な主張が通るわけがない」と感じた。工学の専門家ではない裁判官に対しては丁寧な説明が必要だろうが、それでも異常性は理解されるだろう。また、事故当時の知識や経験が未熟であったために判断能力がなかったと主張するならともかく、現在も「飛行機の性能は安全性と相反する」「試験飛行しなくても安全性は確認できる」と主張する人物が、航空機メーカー等で仕事に就いているのは驚くべきことだ。そんなことはあり得ない。
…そう、そんなことはあり得ない。ここまで答弁書を読み進めてきて、私の脳裏に浮かんだのはそれだ。「いくら何でも、こんな支離滅裂な主張をするわけがない」と。そう考えて他の情報も併せて考えていくと、この答弁書への疑念がさらに深まっていくのである。
チーム側の答弁書は、チーム側の5人の元学生達の意見ではないのではないか、と。